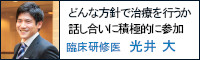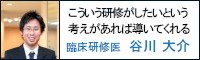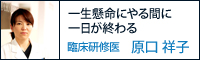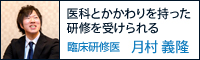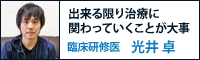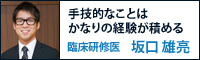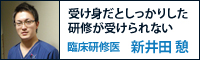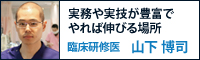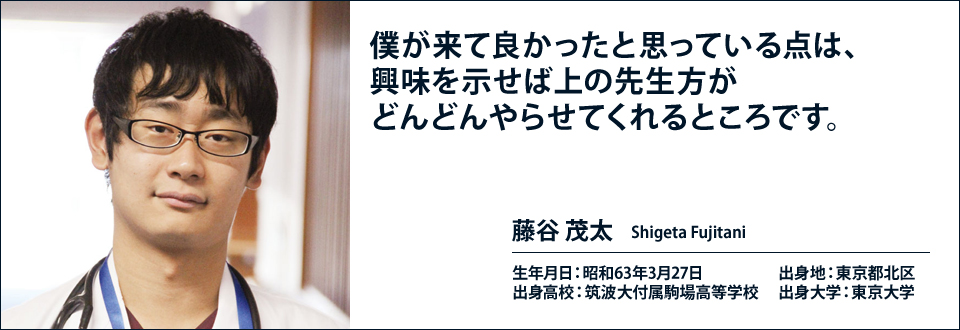
子供の頃は極度の人見知りであまりしゃべらないとても静かな子だったようです。親から聞いた話では、親の声に反応しなさすぎて別に耳が悪いわけでもないのに耳鼻科に連れていかれるほどでした。また、自分の世界に入り込んでしまうような子で、パズルが好きで、例えばジグソーパズルのようなパズルを永遠にやっているような子でした。
親は厳しい方で、小さい頃はいろいろと言われることが多く、勉強は好きな算数や地理などはどんどんやりましたが、嫌いな国語や理科などは避けていて親に怒られることがありました。両親からは何でも教えて貰え、興味があるもの、例えば地図を読むのが好きだったのですが、興味を示すと地図の図鑑のような本などを与えて貰える環境でした。4人兄弟の長男で、中2人は年齢が近く喧嘩をよくしていましたが、総じて仲が良く兄弟が多いのは色々と遊べて楽しいです。兄としてどちらかと言えば消極的で、自分からイニシアティブをとって何か見本になるようなことはあまりなかったため、その辺りで怒られることもありました。父は金融関係の仕事をしており夜遅くなることが多く、母のしつけが凄く怖かったのを覚えています。ゲームボーイのみ買い与えて貰いましたが、あまり家ではやらず友達の家で遊ぶことが多かったです。また段ボールなどでボードゲームを作るなどモノを創るのが好きな子供でした。
父親がとても本好きなため家には文庫本が沢山あり、取り敢えずそこにあるものは手に取って読もうかなというような感じで、難しい本はそれほど読めていませんが、中学生の頃まで小説などをよく読んでいました。なかなか本を読み始めるまでに時間はかかるのですが、小学生向けの本は1日に1冊、長めの難しい小説とかは1週間に1冊程度読んでいました。父の仕事の関係で7才の小2の夏からアメリカに住むことになったのですが、現地でも小説とかを主に読み、漫画は少しですが読んでいました。アメリカでは毎年リーディングマラソンと言って、読んだ本の名前とページ数を書いて提出する取り組みがあり、英語の本はそれで十分で、自分で読む本としては日本語の本が多かったです。基本的に選ぶのが苦手で、図書館などで選ぶと時間がかかるため友達がこの本が良い、と言った面白そうな本を借りて読んだりしていました。
アメリカの学校では、高学年になると日本の教室のように机が並んでいる教室でしたが、低学年の頃は机がなく1クラス20人未満の少人数のクラスで基本は床に座っての授業でした。英語ははじめアルファベットも知らずに苦労しましたが、有難かったのはアメリカには様々な国から来ていて、アジア系だと中国人や韓国人が多くインド人が増えはじめた時期だったのですが、そういう人達が引っ越してくると初めから通常クラスに入ることができないため、1日1~2時間程度、ESL(English as a second Language)という外国人のための第二言語としての英語の授業があり、そこでアルファベットや発音、簡単な文法などを教えて貰い、3ヶ月程度で完全に通常クラスに加わることができるようになりました。小2 の時期でしたので割とコミュニケーションはすぐにとれるようになっていきました。
成績は科目にもよりますが、中学ではA~E までの5段階評価にプラスやマイナスの評価が付くことがあり、得意だったのは数学などで、国語などは普通位でした。アメリカでは義務教育が高校まであり、私立に行くのでなければ自動的に地元の公立学校に通うことになるので、熱心な親とかは教育水準で住む地域を選ぶことがあるようです。中学を卒業する頃には日本に帰国することになり、受験し日本の高校に入学しましたが、アメリカで勉強をしたくてアメリカの私立高校を受験し、ひとりで2 年間留学しました。その後、日本の高校に戻りましたが、余所の単位は1年間迄しか認められないことから、高校は計4年間通ったことになります。アメリカの学校では初めに割り振りテストがあり、3段階位のレベルでクラス分けされます。好きなことはどんどんやり、他の科目は基本的なレベルでいいよと言うような考え方で、またアメリカや日本で通っていた高校には数学オリンピックなどの代表者が多くとても刺激になりました。
アメリカの学生生活では中高校生になるとダンスパーティが催され、私立高校時代は世界中の様々な国の生徒が寮にほぼ住んでいたことから、寮毎に友達と一緒に行くようなダンスパーティが開かれ楽しく過ごしました。卒業時にはプロムと呼ばれる女の子を誘うようなパーティがあるのですが、その時にはすでに帰国していて経験できていません。でも、世界中に友達が出来て、また丁度、私立高校を卒業して日本に戻ってきた頃に始まった『facebook』で最近は疎遠になっていますが今でも繋がりを持っています。
アメリカには日本のような部活が無く、高校に入ると体育の授業の一環としてスポーツチームに入るのですが、本人のやりたいレベル、例えば体育の授業のレベルか、大会出場のための本格的なレベルかを選べるのですが、あまりチームに所属することはせず、体育の授業として近くの川でボートを漕いだりテニスをしたりしました。一方で小さいころからヴァイオリンを習っていましたのでオーケストラのような楽団に所属していました。ヴァイオリンは3才の頃からで、母がピアノをやっていたので何か音楽をやらせたかったのだと思いますが、「何か楽器やってみる?」と、いくつか楽器の名前を挙げ、当時ヴァイオリンは全く知らなかったので知らないものをやってみようと選んだようです。習い始めのころは練習が嫌いで、仕方なくしていた感はあるのですが、ある程度弾けるようになると楽しくなり、今でもたまに弾きたくなることがあります。
もともと物理とかが好きでロボットを作ったり、医療工学とか薬品をつくるのが面白そうだなと思っていたのですが、親戚が大腸がんに罹りあっという間に他界したことに衝撃を受けましたし、また母方の両親が脳腫瘍や脳梗塞などで亡くなったことも影響していると思うのですが医師を目指すようになりました。
医師免許を取得して初めは研究者志望でしたが、医師免許は国から医師を育てるために制限され許可が出ますので、研究で還元できるかわからず、それを還元するために医師免許を貰う以上は臨床医ができるようになりたいと思っています。
06:30 / 起床
07:45 / 出勤
08:00 ~ 17:00 / オペ、翌日オペ、患者さんの問診・投薬・点滴等指示出し
17:00 / カンファ、翌々日のカルテ纏め
19:30 / 帰宅
23:30 / 就寝
会津中央病院は全く知りませんでしたが同期の清水先生から教えて頂きました。スタッフの仕事ぶりを見学させて頂き、とても仕事がしやすそうだなと感じました。また、症例も多く経験できるところということで選びました。
都内に4箇所位の病院を回ったのですが、都内には有名な先生がいたりなどで全国から研修医が集まって来ていますが、会津中央病院は会津全域から患者さんが集まって来て、そこで都会から離れて頑張っていこうと思ったのが一番大きかったです。
見学した時も思ったのですが、スタッフの方々がなんでもやってくれるのでやりやすいのと研修医が何も知らない時に病棟に出ても親切に色々教えて頂けるのでとても心地よいです。それに甘えてはいけないなとは思うのですが…。不器用なので人よりも多くやらなくてはいけないなと感じています。科によって雰囲気は違うとは思うのですが、そんなに研修医が多いわけではないので、上の先生に付きっきりで研修を受けることができる環境は良い点だと思います。
また、ほとんどの先生方が興味を示せばどんどん教えてくれるところが有難く、多少医者の数も少なく忙しいと思うのですが、時間を割いて教えて下さる先生が多くとても感謝しています。
最近日は家で寝てることが多いです。他の研修医の方々が忙しくて以前ほど、どこかに行くことは少なくなりました。車を買ったばかりの頃はひとりで山形や新潟、只見に行ったりしていました。他に趣味の外国語の本を読んだり勉強をしたりしています。結構覚えるまでに時間がかかるので何回も読み返したりしています。
他の先生方も話されていると思いますが、研修医でも一人の医者として患者からは扱われ、いろいろ質問され頼りにされていることは有難く、ちゃんと勉強しないといけないなというモチベーションにもなります。患者さんから退院する時などに研修医の僕に「ありがとう」と言ってくれたりとかちょっとした贈り物のようなものをくださったりなどして頂き、今でもその一人ひとりを覚えています。
初めのうちは知識がなくあまり医学的なことは自信を持ってできずに、できるだけ長い間患者さんと話しをするようにしていたのですが、それを覚えてくれている方がいらっしゃって退院するときに感謝の言葉を言われるのがとても嬉しいです。
また、救急車などで運ばれてきた患者さんが元気になって退院していく姿をみると達成感に満たされますし、良かったと思います。研修医なので自分がその患者さんにどれだけ貢献できたのかはわからないのですが、どんどん経験を積んでいくなかで、悪い状態で来た方を良くして返していくということに関われることが良いのではないかと思います。
実はあまり将来のことは詰めていないのですが、脳にかかわる科は3つ(神経内科、精神科、脳外科)あり、脳外科は麻痺が残ることがあるのですが劇的に治ることもあって、治せている実感が一番あるのかなと思います。1ヶ月間の脳外科研修では、ぐいぐい行く方ではないので外科に向いていないと言われるのですが、努力次第でどうにかできる部分があるのかなと感じています。脳外科に進んで脳出血などの緊急的な治療ができるようになりたいと思っています。しかし、興味があるのは脳のしくみのところだったので、機能外科といって、てんかんなどの治療ができたらいいなとも思います。また、元々研究に興味があるので、ある程度キャリアが積めたところで、脳に関する研究をしてみたいなと思っています。脳については未だにわかっていないことが多く、解明していく面白さがあると思います。研究室にそんなにいりびたっていたわけではないので実際に本格的に研究をやった時にどうなるかはわからないのですが、研究者の方はおよそその研究を始める前に自分でとても細かいところまで予想をしていて、仮説を立ててそれを証明することが研究の基本だと思うのですが、ある程度長い間、様々な患者さんを診てきて、たぶんこうなのではないかと細かいところまで掘り下げていて、そういう予想をたてることが本当にうまいと感じています。それを言うためにこういうピースが必要だというようにそういうところを診ていくことができれば自分もやっていきたいです。そこまでの才能があるのかはわからないのですが、ある程度臨床医を続けていけたなら患者さんを診てきて何か気づく点があるだろうと思います。そういうことに気付くためにもっと患者さんを診ていかなければならないと感じています。
昔はもの凄い人見知りで、高校生位から一気に変わりましたが今でも人見知りではあるので、最初病棟に出た時などは辛かったのですが、人とかかわりを持つ職業なので患者さんと関わる以上はしっかり時間の許す限り話を聞いてあげて、初めに山岸先生に言われたことなのですが、「患者さんは病気だけではなくて全人的に診ないといけない」と、生活背景とかもそうですし、しっかり人間として患者さんに接して、その病気だけでなくて生活行動も考えた治療をしていける医師になりたいと思っています。