胸腔鏡手術と肺癌との関わり
低侵襲性治療としての胸腔鏡手術と肺癌との関わり
身体のなかにはいろいろな空洞のような空間(体腔といいます)があり、代表的なものが胸部の胸腔と腹部の腹腔です。呼吸器疾患は胸腔(肋骨・胸骨・胸椎、肋間筋、横隔膜などで囲まれた空間)の中にある肺、縦隔臓器(左右胸腔に囲まれた領域)、胸膜、胸壁などに起こる病気が呼吸器外科治療の対象となります。肺・縦隔疾患に対する外科治療は伝統的には後側方開胸、側方開胸、胸骨正中切開など15 ~ 30cm の胸壁の皮膚・筋層を切開・切離し、さらに肋骨を切除して胸腔内に到達します。胸骨正中切開では胸壁全面の真ん中にある胸骨を手術用鋸で切り離して縦隔や胸腔にアプローチする開胸法(胸腔に入るためのアプローチ)が1990 年前半まで一般的な方法でした。しかしこの開胸法は胸壁の破壊が大きく身体が弱い人、心臓が悪い人、肺が悪い人、高齢者の患者さんにとっては大変な身体的負担になり、手術を諦めなければならないこともあり、また頑張って手術を受けても手術後に大変な苦労をすることもあり、また日々の生活にも支障を来してしまい、医師、患者さん双方にとって大きな課題となっていました。
「何とか患者さんの負担を軽減できないか」という試みは20世紀初頭に遡ります。呼吸器外科の世界ではひとつの革命といえる出来事、1915年、スエーデンのJacobeusによる膀胱鏡を用いた肺結核治療後の胸腔内観察の試みでした。我が国においても戦後に木本らにより試みられましたが当時の器材では手技的に非常に困難であることから普及には至りませんでした。それから長い時間を経て1980年代後半に光学機器の発達を背景に先駆者らの努力で現在の胸腔鏡手術が開発され燎原の火のごとく全世界に普及していきました。
ここからは、胸腔鏡手術と呼吸器外科手術のなかで最も関心がもたれた肺癌と外科治療の関係についてお話ししたいと思います。呼吸器外科学は20世紀半ばまでは肺結核外科治療として発展してきましたが、薬物治療の進歩に伴い内科的治療が主役となり、その知識・技術はそのまま増加してきた肺癌外科治療へと引き継がれていきました。(図3)
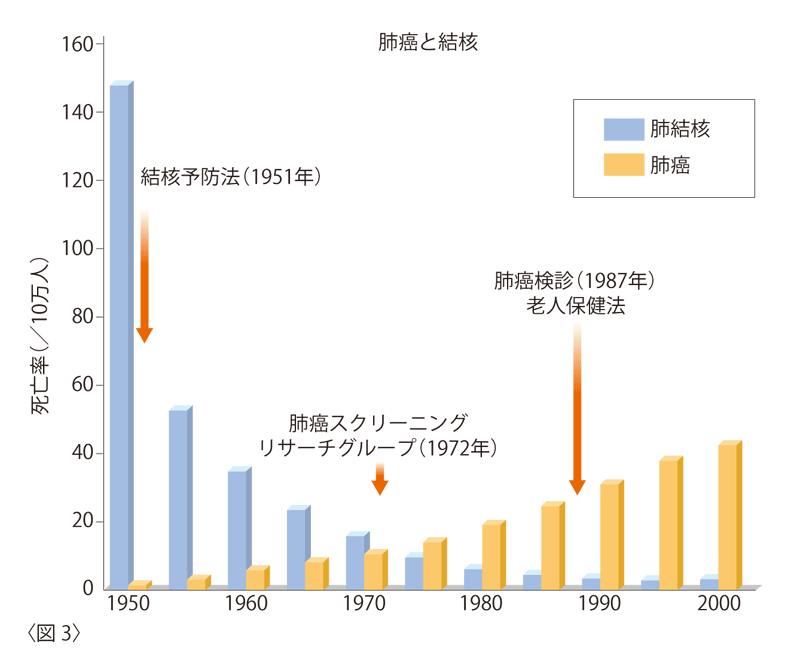
肺癌は現在では悪性腫瘍による死因の第1 位となっていますが、1950 年頃は肺結核が死病として恐れられ、人口10 万に対して150人位が肺結核で亡くなられていました。太平洋戦争(大東亜戦争開戦時)には若くして肺結核死する率が高くの日本の平均寿命は47 歳でした。一方で肺癌発症は平均65±3 歳位ですので当時の日本には肺癌患者は非常に稀といってもよいくらいでした。その当時欧米の平均寿命は60~61 歳ですので1960 年代でも肺癌は欧米に多く日本には少ないとの認識でした。しかし、1950 年の結核予防法の全面改正により、肺結核死亡数は劇的に減少し、結果として日本人の平均年齢は着実に延長しました。一方で平均寿命の延長にともない肺癌を発症する人口が増加し始め、1960 年には早くも現在の日本肺癌学会が創設され、1970 年代には肺癌死亡率が肺結核死亡率を凌駕し一躍社会問題として人々の最大の関心事となってきました。これを重く見た我が国は1972 年に「肺癌スクリーニング研究班」を立ち上げ、人口10 万に対する肺癌死亡が20例以上になった時点で老人法に基づき1987 年「肺癌検診」が始まりました。そして1998 年には肺癌はついに死因の第一位となりました。肺癌死亡は50,000 人を上回り、すべての癌死の約18% を占めるまでに増加しました。肺癌発生率は2015年までに約150,000 に昇ると予想されました。肺癌検診の普及に伴い1990 年代に入り胸部CT スキャンが画像診断に積極的に応用されるようになりました。これにより胸部X線写真では発見が困難な非常に早期に発見される肺の隅の方にできた小型肺癌(図4A)の発見率が高くなりました。(図4B)
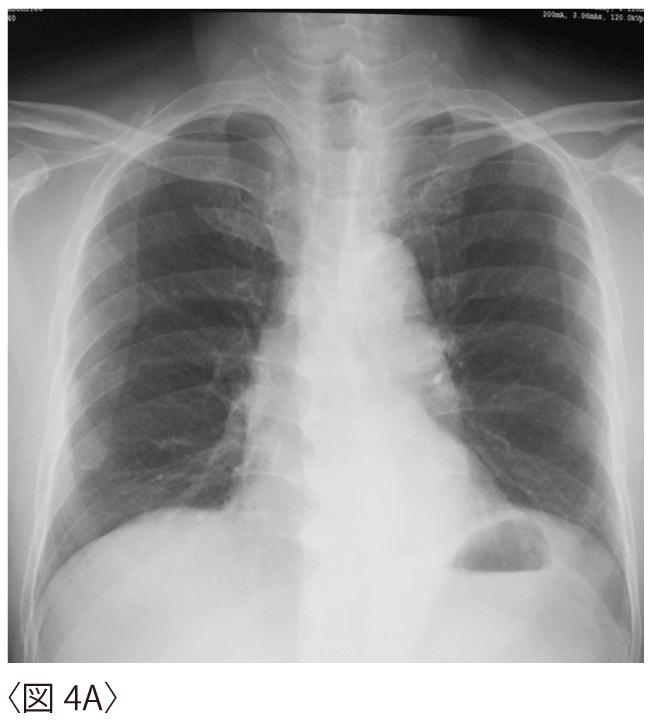
一方で1980 年くらいまでは多かった太い気管支にできる扁平上皮癌が少なくなり、胸を大きく切る伝統的な後側方開胸のような大きな開胸法が不必要なだけでなく高齢者や余病を持つ患者さんにとって大きな負担となり、手術に耐えられない患者さんや手術後の体力維持が困難で、さらに十分な社会的活動が出来ないまま亡くなられる患者さんが少なくないことが詳細な臨床研究で明らかになってきました。
そこで注目されたのが患者さんの身体に不必要な負担を掛けない胸腔鏡手術の出現でした。
ここまで肺癌を中心に呼吸器外科の歴史をお話ししてきたのは胸腔鏡手術が注目され開発された背景をお話ししたかったためです。1970 年代前半では、発見され病院を訪れる患者さんの約7 割ほどがすでに高度の進行癌であり、治療法は限られており予後は極めて悲観的なものでした。1980 年代から90 年代の中頃くらいまでは高度の進行癌を何とか克服するために肺の周りの臓器を一緒に切除する拡大合併切除も盛んに行われました。しかし時代とともに平均寿命の延長と高齢化が進み、さらに胸部CT スキャンによる早期小型肺癌の発見率の増加と相まって「低侵襲的に胸腔内の診断から治療を可能にする」胸腔鏡手術が開発されていったのは時代の必然ともいえます。

